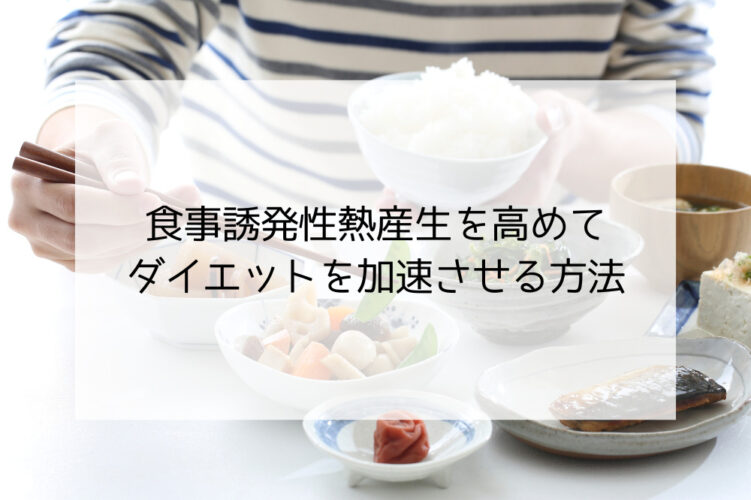私たちが普段消費するカロリーは、基礎代謝と活動消費カロリーの他にDIT(食事誘発性熱産生)というものがあります。
このDITはちょっとした工夫で高めることができるので、ダイエットを成功させるためにも知識をつけてうまく食事制限をしていきましょう。
基礎代謝量は最低限必要なカロリーともいわれ、平均して食事から摂取する必要があります。
食事誘発性熱産生をもう少しわかりやすく

DITは食事誘発性熱産生のことで、食事をした際に食べ物を咀嚼したり、消化・発酵・吸収する過程でで消費されるカロリーのことを言います。(DITはDiet induced Thermogenesisの略)
このDITは食事の内容やその時の状況、食べ方や温度によって変化するため、DITを高める行動をとることで、1日の消費カロリーを増やすことができます。
効率よくダイエットを進めるためにも食事誘発性熱産生を上げてどんどん体重を落としていきましょう୧(๑›◡‹ ๑)୨
食事誘発性熱産生を高める食べ物 おすすめはプロテイン

食事誘発性熱産生は食べる食材によって数値が変わります。
| 栄養素 | カロリーに含まれるDITの割合 |
|---|---|
| たんぱく質 | 約30% |
| 脂質 | 約4~10% |
| 炭水化物 | 約5~20% |
脂質は高カロリーなうえに食事誘発性熱産生も少ないため摂取しすぎると、肥満になる可能性もあるので注意が必要です。一方、たんぱく質は筋肉を作るのに大切な栄養素であり、食事誘発性熱産生も低いため積極的に摂りたい栄養素だといえます。
肉類、魚介類、卵類、大豆製品、乳製品
肉類は脂質を含むものは避け、鶏のささみや赤身肉などを中心に摂取するとカロリーを抑えることができます。プロテインもたんぱく質なので筋トレ後や就寝前に摂取すると効果的です。
食事誘発性熱産生を高めるためにも、普段からPFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物の摂取バランス)を意識するようにしましょう。
食事性誘発性熱産生の計算方法

食事誘発性熱産生はその時の状況によって微妙に変化するため、計算だけで確実な数値を出すのはとても難しいとされています。しかし、ざっくりであれば計算も可能ということで、ネット検索すると自動で計算してくれるサイトも存在します。
具体的に計算する場合には上の栄養素別の食事誘発性熱産生を計算していきます。
例えば1日の摂取カロリーがたんぱく質60g、脂質30g、炭水化物150gだった場合、それぞれのカロリーと食事誘発性熱産生は以下のようになります。
| 量 | カロリー | DIT | |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 80g | 320kcal | 96kcal |
| 脂質 | 40g | 360kcal | 14~36kcal |
| 炭水化物 | 150g | 600kcal | 30~120kcal |
| 合計 | 1280kcal | 140~252kcal |
それぞれ摂取カロリーのうち食事誘発性熱産生の割合は、たんぱく質の30%、脂質の4~10%、炭水化物の5~20%と言われているので、計算するとこのような数値になります。
メニュー別食事食事誘発性比較

ここで、脂質が多いメニューとたんぱく質が多いメニューの食事誘発性熱産生を比較してみます。
比べるのはラーメンと親子丼と筋トレ弁当。筋トレ弁当はトレーニングをしている人が良く食べているささみと卵とブロッコリー入りのお弁当です。
ラーメンは脂質が多いメニュー、親子丼は3大栄養素がバランスよく摂れるメニュー、筋肉弁当はたんぱく質が多いメニューになります。
| 食事メニュー | 食事誘発性熱産生 |
|---|---|
| ラーメン | 約55kcal |
| 親子丼 | 約70kcal |
| 筋トレ弁当 | 約101kcal |
ラーメンは1食で消費する食事誘発性熱産生が少ないのがわかります。
1食だけだと100kcalも変わらないのでそれほど違いを感じにくいかもしれませんが、長く続けることで大きな差が生まれます。
ラーメンなら豚骨より塩、豚骨にしたいなら背脂たっぷりよりあっさりがおすすめです。(親子丼なら脂が少ない皮なし胸肉がおすすめです。)
食事誘発性熱産生が高い人の特徴

栄養素だけではなく、食事のとり方を工夫することでも食事誘発性熱産生を高めることができます。以下は食事誘発性熱産生が高い人・低い人の特徴です。
| 消費エネルギー量→ | 高い | 低い |
|---|---|---|
| 運動習慣 | あり | なし |
| 体温(平熱) | 高い | 低い |
| 食事の時間帯 | 早い | 遅い |
| 食事環境 | リラックス | あわただしい |
| 味覚① | おいしい | おいしくない |
| 味覚② | 辛い | 甘い |
| 料理の温度 | 温かい | 冷たい |
| 咀嚼 | よく噛む | よく噛まない |
表を見てわかるように、普段から運動する習慣があり、リラックスした状態でおいしい料理をよく噛んで食べる人は食事誘発性熱産生が高いことが分かります。
逆に、夜遅い時間に甘くて冷たい食べ物をあわただしくほとんど噛まずに食べるような人は食事誘発性熱産生が低く消費カロリーも低下してしまいます。
食事誘発性熱産生は気にしなくてもダイエットを進めることはできますが、知っておくことでより楽に痩せることができるので、うまく利用していきましょう。
食事誘発性熱産生が上昇すると汗をかく理由

食事誘発性熱産生(DIT)が上昇すると汗をかく仕組みは、体温調節のための反応に基づいています。食事後、特に消化・吸収や代謝が行われると、エネルギーが熱として放出されます。
この熱の増加により体温が上昇し、体は一定の温度を守るために「熱放散」を行います。その中核的な役割を果たすのが汗の量です。
汗をかく仕組みを具体的に説明すると、まず体内で生成された熱は、皮膚表面に移動して放散されます。このとき、交感神経が活性化され、汗腺から汗が分泌されます。分泌された汗は皮膚表面で蒸発し、その際に気化熱を奪うことで体温を下げる効果を発揮します。
DITが増加する食事(例えば、たんぱく質が多い食事や香辛料を含む食事)を摂取すると、代謝活動が一時的に増加し、それに伴って熱産生も多くなります。汗の量が増えるのです。
また、DITが特に暑い環境や体を動かした後など、かなり体温が高い状態では、DITによる汗の量が増えるとされています。
食事誘発性熱産生を高める運動法

加齢や運動不足などで筋肉量が低下すると基礎代謝だけではなく、食事誘発性熱産生も低下することがわかっています。
上の表でもご紹介したように運動習慣をつけると食事誘発性熱産生を上げることができます。基本的にはどのような運動でも良いのですが、筋量を上げることで食事誘発性熱産生も上がるため筋トレを行うとより効果的です。
筋トレというとジムでバーベルやマシンを使ったようなハードなものを想像しがちですが、家で簡単にできるスクワットや腹筋などでも十分に効果はあります。
また、駅やショッピングモールなどで階段を多く使うことでも筋力を向上させることができますのでぜひ普段の生活に取り入れてみてください(๑•̀.•́ฅ✧